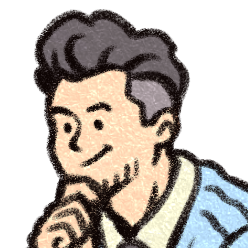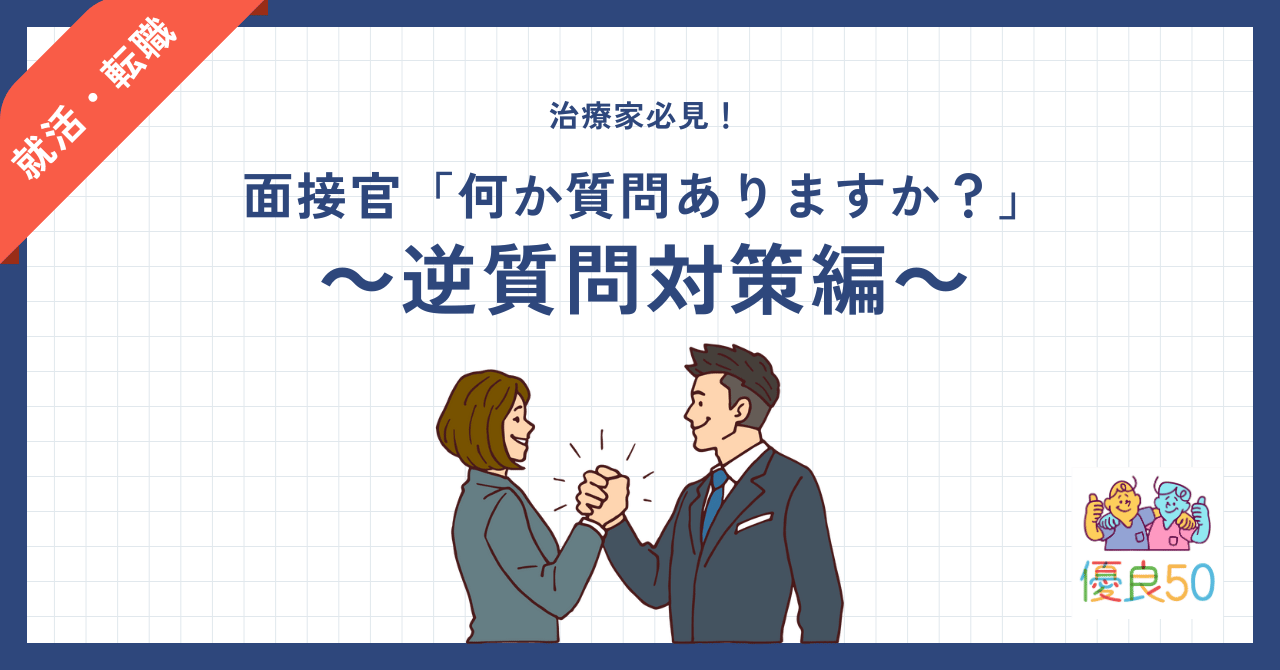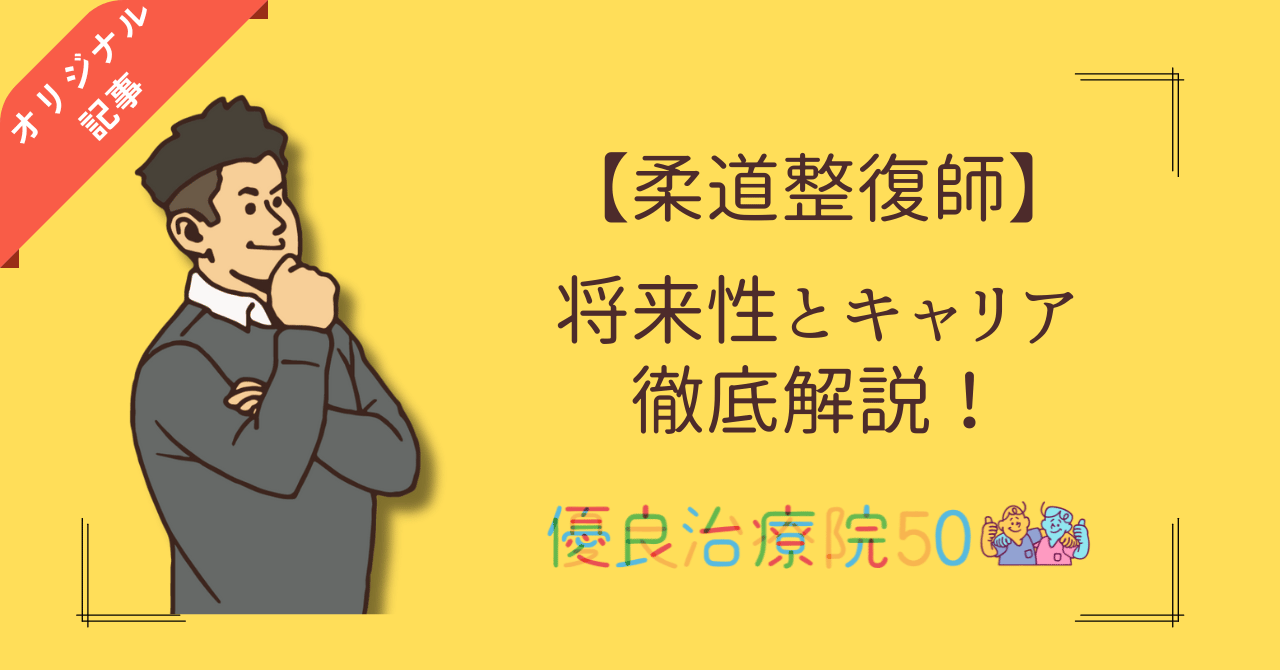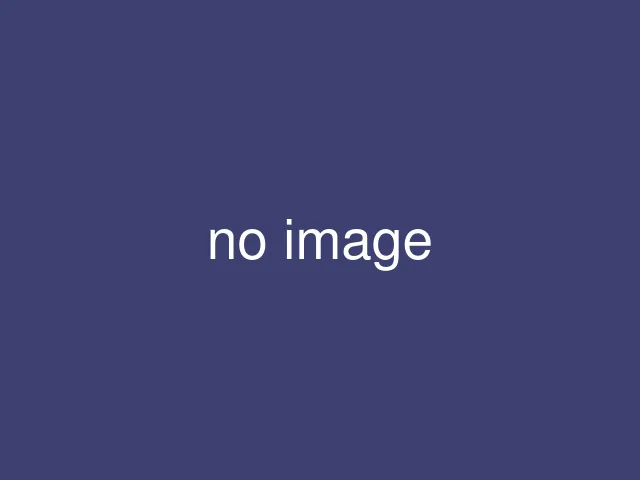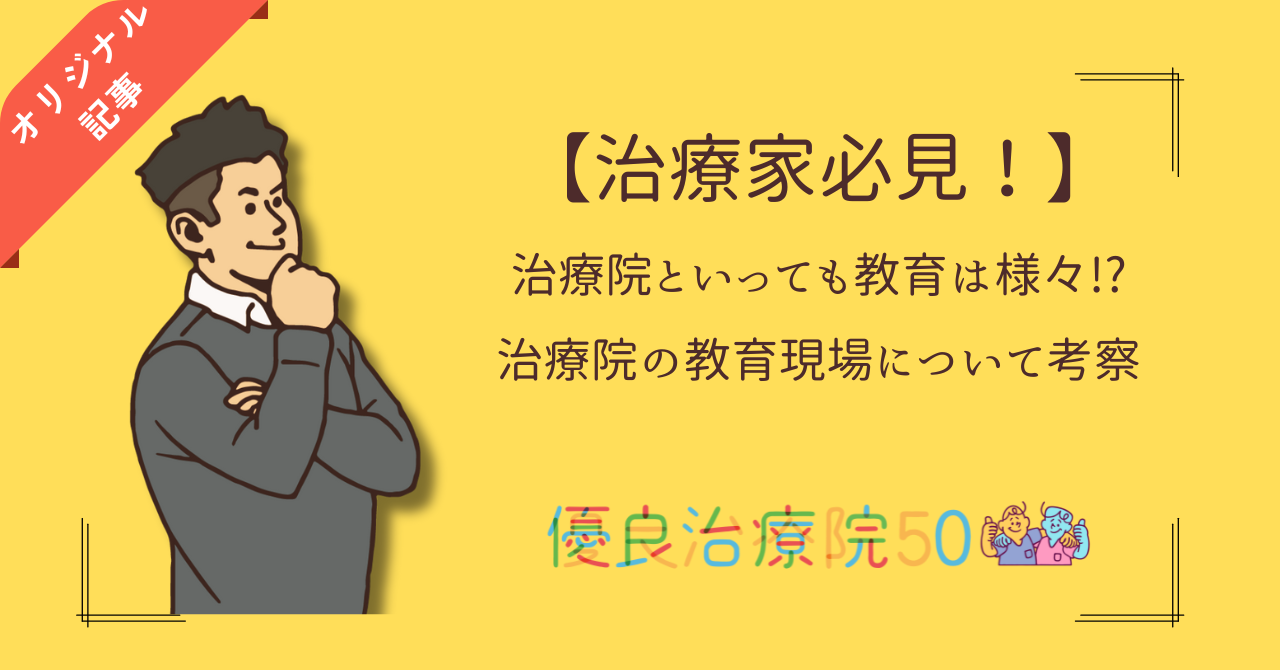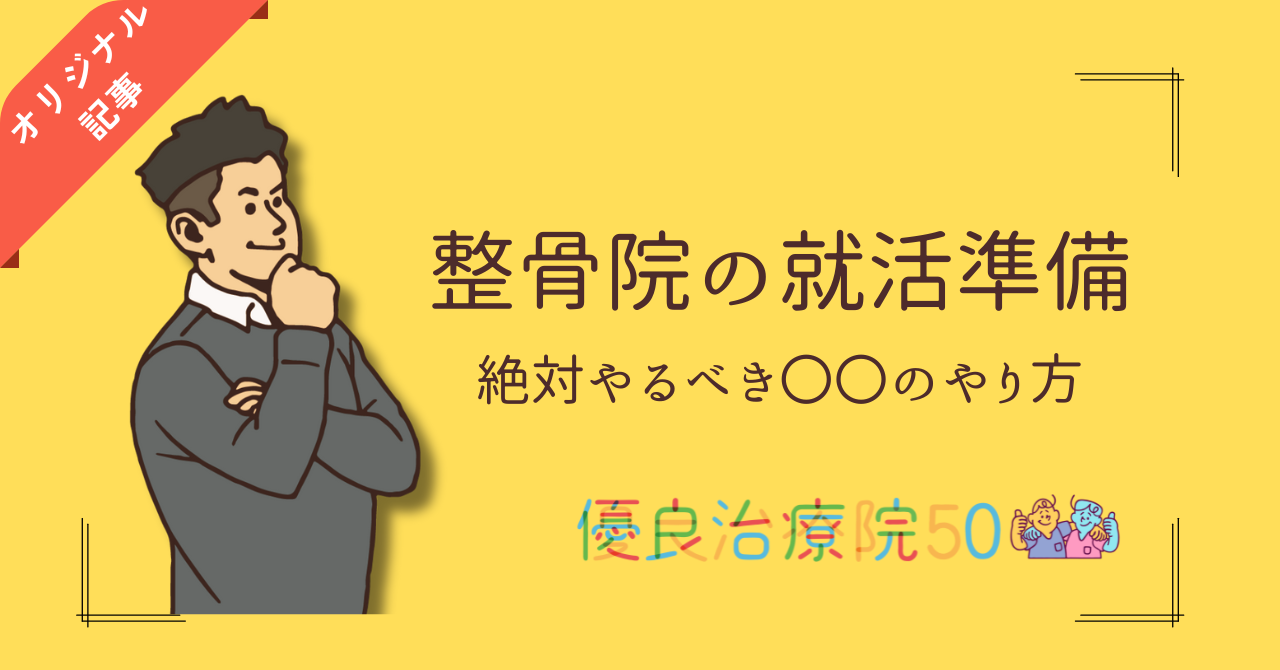スポーツのトレーナー資格はどれがいい?主要9資格の難易度、働ける職場を徹底比較
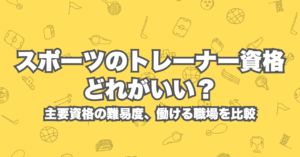
「好きなスポーツをいつか仕事にしたい…」
そんな方にとって、スポーツ現場で活躍するカギとなるのが資格取得です。
しかし、実は日本には「スポーツトレーナー」という名前の国家資格は存在しません。
民間資格と国家資格をしっかり比較し、自分の将来像に合った資格を選ぶことが重要です。
本記事を読みながら全体像を理解し、進路選びの第一歩を踏み出しましょう。
1986年生まれ。千葉市出身。3児の父。 2018年(株)じんじあいであ設立。 治療院業界の「就職支援センター」になるべく、若手治療家の転職相談やキャリア相談を受けています。圧倒的技術を身に付けたい人から、スポーツ現場でトレーナーとして活躍したい人まで、学校選び〜就職先の選び方まで全力サポートしています!
スポーツトレーナー資格の種類【一覧】
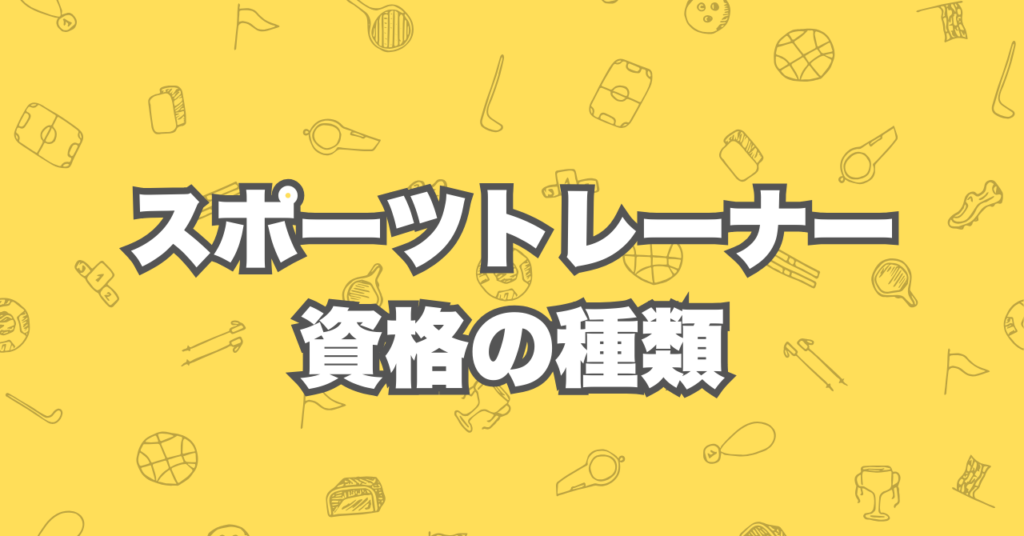
ここでは、トレーナーに関連する代表的な 国家資格 と 民間資格 を一覧表にまとめました。
| 種類 | 資格名 | 取得方法 | 活動範囲 | 開業可能か |
|---|---|---|---|---|
| 国家資格 | 柔道整復師 | 専門学校・大学 → 国家試験 | 外傷・接骨 | 可能 |
| 国家資格 | 鍼灸師 | 同上 | コンディショニング、慢性痛 | 可能 |
| 国家資格 | あん摩マッサージ指圧師 | 同上 | リハビリ・疲労ケア | 可能 |
| 国家資格 | 理学療法士(PT) | 同上 | 病院・リハビリ現場中心 | 不可能 |
| 民間資格 | NSCA-CPT、NSCA-CSCS、NESTA-PFT、JATI-ATI、JSPO-ATなど | 講習+試験 | ジム・チームサポート | 可能 |
国家資格は医療や治療に関われる点で信頼性が高く、将来のキャリア幅が広いことが分かります。
国家資格と民間資格の違いは?
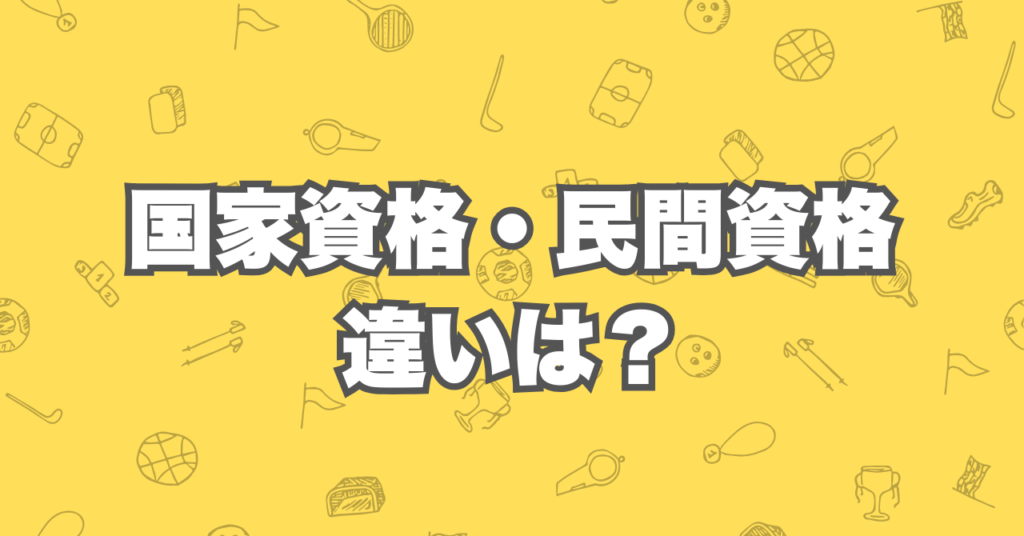
スポーツトレーナーを目指す上で、最初に押さえておきたいのが 国家資格と民間資格の違い です。
国家資格の特徴
- 厚生労働省や文部科学省が認可する公的資格
- 専門学校や大学で数年学び、国家試験に合格して取得
- 医療行為・独立開業が可能
- 信頼性が高く、就職・独立いずれにも強い
民間資格の特徴
- 民間団体や協会が発行する認定資格
- 数ヶ月の講習や独学で取得可能
- 活動範囲はトレーニング・コンディショニングに限定
- 開業や医療行為は不可
つまり、民間資格は現場に早く出やすい一方で、国家資格は取得に時間がかかる代わりに「一生モノ」として幅広く活躍できる強みがあるのです。
スポーツトレーナーを目指せる4つの国家資格
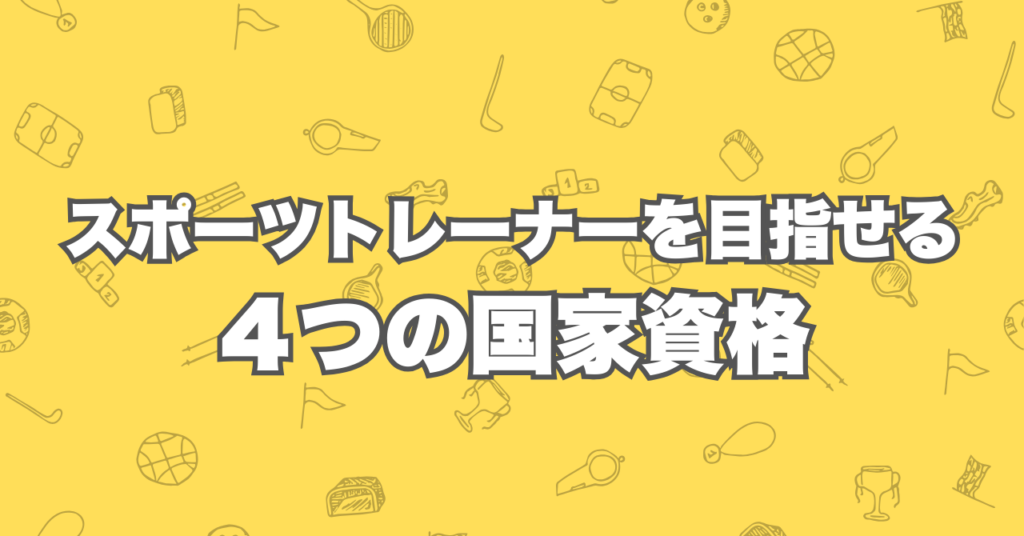
では、具体的にどのような国家資格があり、どのようにスポーツ現場で役立つのでしょうか。
国家資格1:柔道整復師
柔道整復師は「ケガ対応のスペシャリスト」です。
柔道整復師の特徴
- 業務範囲:骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの施術
- 専門分野:スポーツ外傷・応急処置・リハビリ
- 活躍現場:接骨院・整骨院、スポーツチーム、病院
捻挫や骨折といった突発的な外傷に対応でき、リハビリや競技復帰のサポートも行える国家資格です。
接骨院を独立開業できるため、将来的に安定したキャリアを築ける点も魅力です。
国家資格2:鍼灸師
鍼灸師は「体調を整える専門家」として、プロスポーツチームでも重宝されています。
鍼灸師の特徴
- 業務範囲:鍼や灸による治療、慢性疾患や疲労のケア
- 専門分野:東洋医学・予防医学・コンディショニング
- 活躍現場:鍼灸院、整骨院併設、病院リハ科、スポーツチーム帯同
慢性的な痛みの緩和から、日々の疲労回復・ケガの予防まで幅広く対応できるため、選手のコンディショニングに直結する資格です。
国家資格3:あん摩マッサージ指圧師
あん摩マッサージ指圧師は「回復と予防」の専門家です。
あん摩マッサージ指圧師の特徴
- 業務範囲:指圧・マッサージによる血流改善、リハビリ補助
- 専門分野:慢性疲労・機能回復・健康増進
- 活躍現場:病院、リハビリ施設、高齢者施設、スポーツクラブ
選手の疲労回復や、長期的なケガ予防に強く、高齢者施設や地域のリハビリ現場でも活躍の幅が広がります。
国家資格4:理学療法士(PT)
理学療法士は医療分野でのリハビリ専門職です。
理学療法士(PT)の特徴
- 業務範囲:医師の指示に基づく運動療法・物理療法
- 専門分野:医療リハビリ全般
- 活躍現場:病院・クリニック・リハビリ施設
スポーツトレーナーを名乗るわけではありませんが、スポーツ整形やリハビリ病院でアスリートの復帰に関わるケースが増えています。
国家資格保持者が活躍できるフィールド・職場
国家資格を持つと、スポーツ現場ではもちろんその他でも活躍の場は一気が広がります。
- 医療現場:病院やクリニックで治療に携わる
- 独立開業:整骨院・鍼灸院・マッサージ院を経営できる
- スポーツ現場:プロチーム・学生チーム・実業団で選手サポート
- 地域社会:高齢者施設や地域リハビリの担い手
特にスポーツ現場では「指導+治療」ができる人材が重宝されます。
国家資格があることで、単なるトレーニング指導だけでなくケガ予防や外傷対応まで担えるため選手やチームからの信頼度は圧倒的に高まります。
スポーツトレーナーを目指せる5つの民間資格
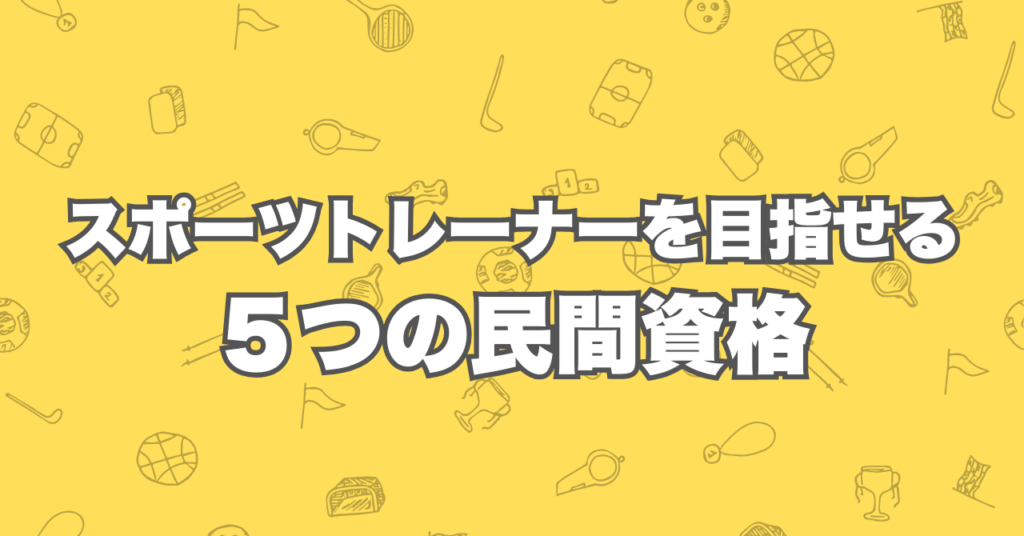
国家資格に比べて短期間で取得できるのが民間資格の魅力です。
特にフィットネスクラブやパーソナルジムで働きたい人には大きな武器になるでしょう。
ただし、医療行為や独立開業はできない ため、将来長く安定して活動したいなら国家資格と組み合わせてキャリアを考えることが重要です。
民間資格1:NSCA-CPT(認定パーソナルトレーナー)
NSCA-CPTは、パーソナルジムで働きたい人にとってスタンダードな資格です。
NSCA-CPTの特徴
- 特徴:世界的に知名度が高く、日本でもパーソナルトレーナーの登竜門的資格
- 取得方法:受験資格(高校卒業程度+AED・CPR講習修了)があれば受験可能
- 活躍現場:フィットネスクラブ、パーソナルジム
解剖学や運動生理学など科学的知識に基づき、個人の目的に合わせたトレーニングを指導できます。
就職募集で「NSCA-CPT保持者優遇」とされるケースも多く、フィットネス業界での信頼性は抜群です。
民間資格2:NSCA-CSCS(認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト)
CSCSは「競技者を対象とした指導」に特化しており、プロチームや学生アスリートのパフォーマンス向上に直結します。
NSCA-CSCSの特徴
- 特徴:アスリートやチームスポーツのための専門資格
- 取得方法:大学卒業(学士号)が受験条件
- 活躍現場:大学スポーツ部、実業団、プロチーム
大学やプロチームのトレーナーはCSCS保持者が多く、国内外で高い評価を受けている資格です。
民間資格3:NESTA-PFT(認定パーソナルフィットネストレーナー)
NESTA-PFTは、初心者でも取り組みやすいトレーナー資格です。
NESTA-PFTの特徴
- 特徴:国際的に認められ、日本国内のジムやスタジオでも導入が多い
- 取得方法:講習+試験で取得可能、オンライン対応もあり
- 活躍現場:フィットネスクラブ、パーソナルジム、健康増進施設
取得に大学卒業などの条件はなく、働きながらでも挑戦可能。幅広い層のクライアントに対応できるので、副業から始めたい人やフリーランス志向の人に人気があります。
民間資格4:JATI-ATI(日本トレーニング指導者協会 認定トレーニング指導者)
JATI-ATIは、日本独自の資格で、トレーニングの基礎から応用まで幅広く学べます。
JATI-ATIの特徴
- 特徴:日本人向けのトレーニング理論に基づく指導資格
- 取得方法:養成講習+試験
- 活躍現場:フィットネスクラブ、学生スポーツ指導、公共施設
地域スポーツや学校教育とも親和性が高く、国内のスポーツ現場で働くには有効な資格の一つです。
民間資格5:JSPO-AT(日本スポーツ協会 公認アスレティックトレーナー)
JSPO-ATは「選手のケガ予防・救急対応・リハビリ・コンディショニング」を体系的に学べる資格です。
JSPO-ATの特徴
- 特徴:日本で最も認知度の高いスポーツトレーナー資格の一つ
- 取得方法:日本スポーツ協会の指定養成課程修了+試験
- 活躍現場:プロ・アマチュアスポーツチーム、大学、医療機関
プロ野球やJリーグなどトップレベルのチームでも採用されており、アスリートのサポートを本格的に行いたい人に向いています。
スポーツ現場で強い!国家資格の魅力
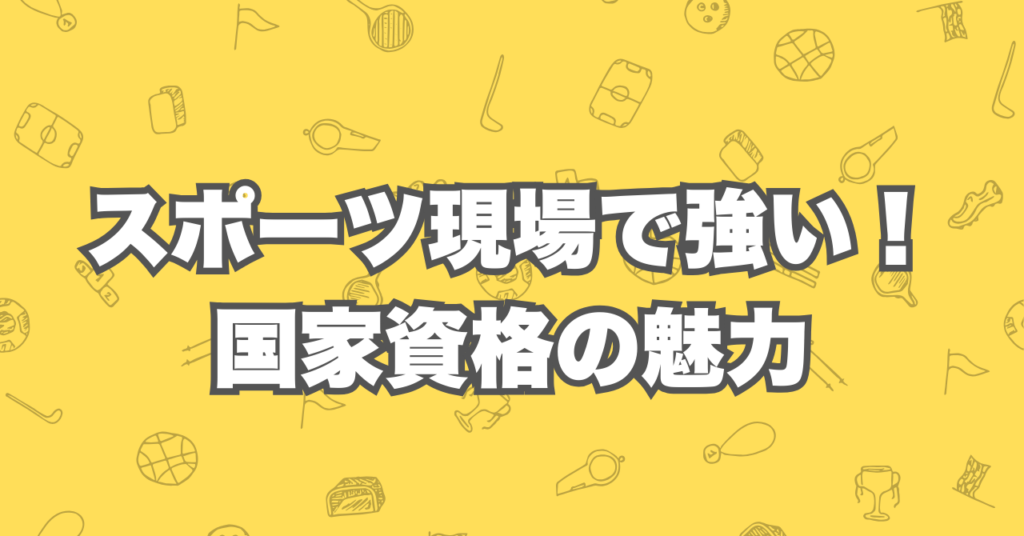
民間資格は短期間で取得でき、フィットネスクラブやジムで活動するには十分です。しかし、スポーツ現場で深く選手を支えるには限界があります。
そこで強みを発揮するのが、柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師といった国家資格です。
これらは専門学校や大学で学び、国家試験に合格することで取得でき、医療行為や独立開業が認められています。
例えば、試合中の捻挫や骨折といった外傷は民間資格では対応できませんが、柔道整復師なら正しい施術が可能です。鍼灸師は疲労回復や痛みの緩和に強みを持ち、チーム帯同トレーナーとしても高く評価されています。さらに、あん摩マッサージ指圧師はリハビリや慢性疲労の改善に貢献し、長期的なパフォーマンス維持を支えます。
このように、国家資格は取得に時間と努力を要する一方で、選手のケガを防ぎ、治し、復帰を支えるという本質的な役割を担える資格です。
だからこそ「国家資格はスポーツ現場に強い」と言えるのです。
【徹底比較】スポーツに強い国家資格&民間資格の資格一覧表
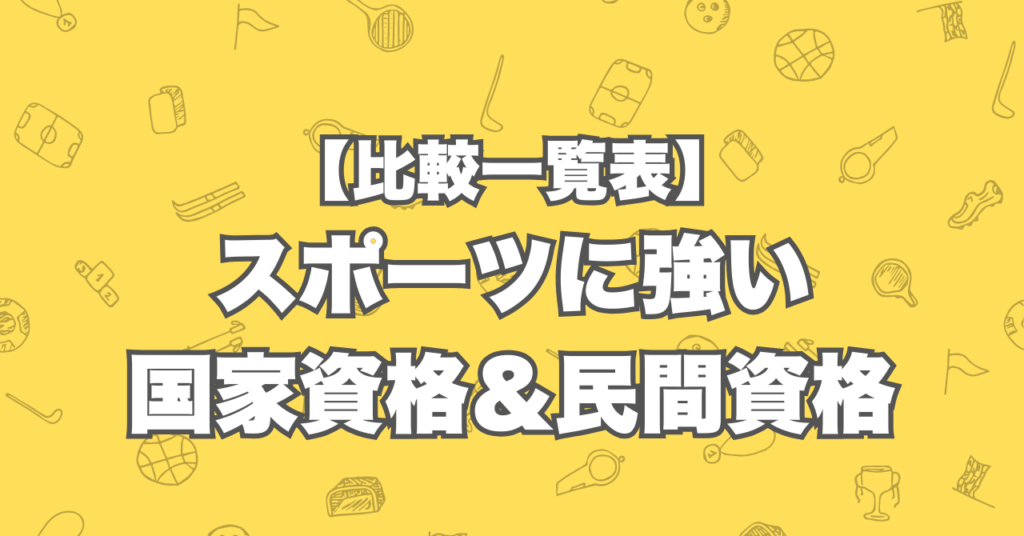
スポーツトレーナーを目指す上で、多くの人が悩むのは「結局どの資格を選べばいいのか?」という点です。
国家資格と民間資格では、学習期間や費用だけでなく将来のキャリアや活動できる範囲が大きく異なります。
ここでは代表的な資格を比較し、特徴をわかりやすくまとめました。
| 資格 | 取得難易度・期間 | 費用目安 | 活動範囲 | 開業可否 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柔道整復師 | 高/3年(専門学校) | 約300〜400万円 | スポーツ外傷対応、整骨院 | 可能 | ケガ対応や独立開業を視野に入れたい人 |
| 鍼灸師 | 高/3〜4年 | 約300〜400万円 | コンディショニング、疲労回復、チーム帯同 | 可能 | 選手の体調管理や東洋医学に関心がある人 |
| あん摩マッサージ指圧師 | 高/3年 | 約300万円前後 | リハビリ、慢性疲労ケア | 可能 | 幅広い世代のケアやリハビリに関わりたい人 |
| 理学療法士(PT) | 高/4年(大学中心) | 約400〜600万円 | 医療リハビリ、病院勤務 | 不可能 | 医療現場での専門性を重視したい人 |
| NSCA-CPT/NESTA-PFT | 中/数ヶ月〜1年 | 数万円〜20万円 | ジム・フィットネスクラブ | 可能 | フィットネス業界で早く働きたい人 |
| NSCA-CSCS/JSPO-AT | 中〜高/1〜2年 | 数万円〜30万円 | 大学スポーツ、プロチーム帯同 | 可能 | アスリート指導や競技現場で活動したい人 |
この表からも分かるように、国家資格は取得までのハードルは高いものの、開業や医療行為まで担える点で将来の安定性が圧倒的に強いのが特徴です。
一方で、民間資格は短期間で挑戦でき、まずはスポーツ現場に入りたい人に向いています。
最終的に「スポーツを一生の仕事にしたい」と考えるなら、国家資格を軸にキャリアを設計するのが有利です。
スポーツ現場で求められるスキルとは?
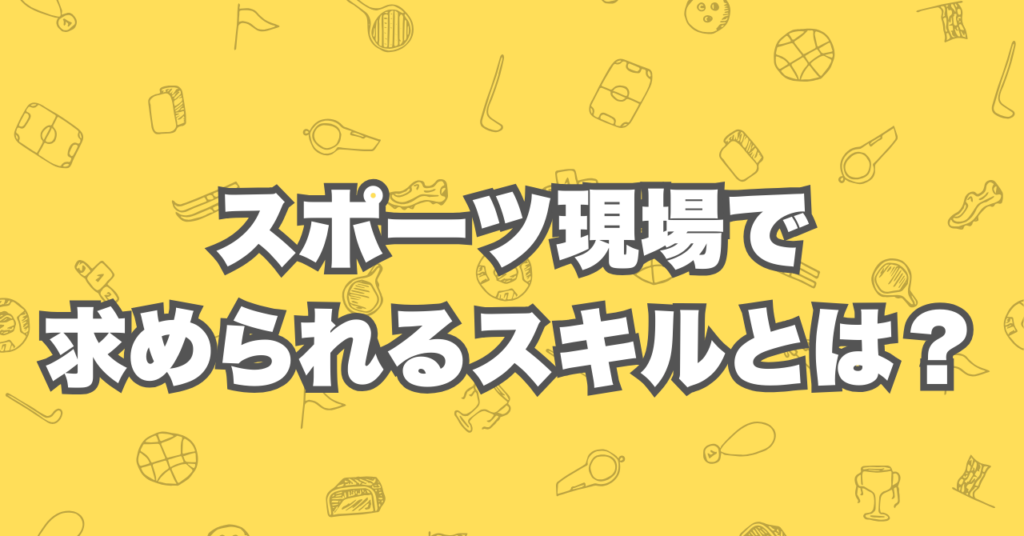
スポーツトレーナーは単に筋力トレーニングを教えるだけの存在ではありません。
実際の現場では、選手の安全を守り、パフォーマンスを最大限に引き出すために幅広い知識とスキルが求められます。
まず重要なのが 外傷対応力 です。サッカーでは足首の捻挫、野球では肩や肘の障害、バスケットボールでは膝の故障など、競技ごとに起こりやすいケガがあります。こうしたトラブルが発生した際、国家資格を持つ柔道整復師なら適切な応急処置や施術ができ、選手の復帰を早めるサポートが可能です。
次に欠かせないのが コンディショニングと疲労回復。ハードな練習や試合をこなすアスリートにとって、疲労管理は成績に直結します。鍼灸師であれば、鍼や灸を使って疲労を軽減したり、慢性的な痛みを緩和したりできるため、選手のパフォーマンス維持に直結します。
さらに、長期的なパフォーマンス維持や再発予防 も大切な役割です。あん摩マッサージ指圧師は筋肉や関節を整えることで慢性的な不調を改善し、競技寿命を延ばすことに貢献できます。これはスポーツキャリアの長い選手にとって大きな価値です。
このように、スポーツ現場で活躍するためには、トレーニング指導だけでなく「ケガの予防」「外傷対応」「疲労回復」「リハビリ」といった多角的なサポート力が求められます。
国家資格で学ぶ知識と技術は、まさにこうした総合的な役割を果たすための大きな強みなのです。
資格取得を目指す学校の選び方
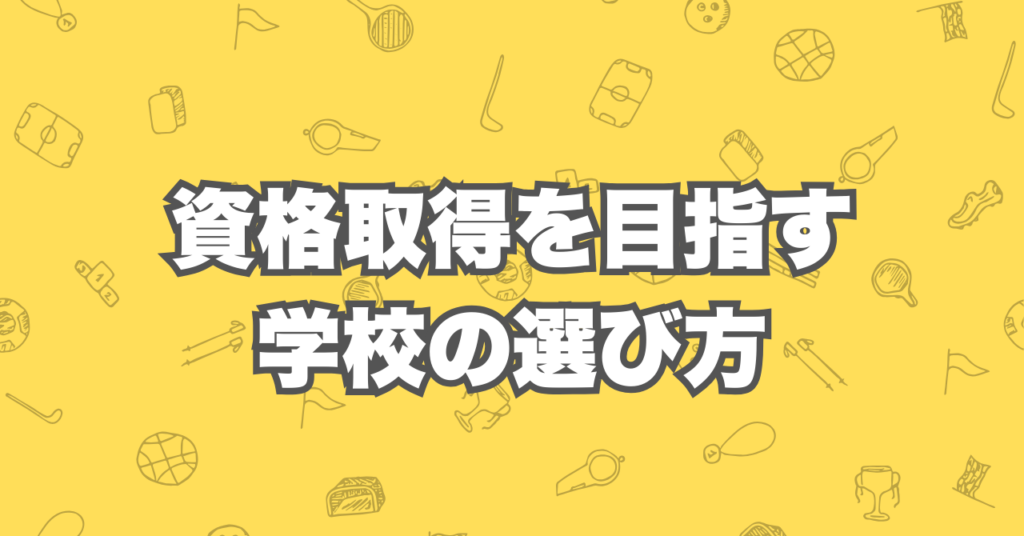
スポーツトレーナーを目指すうえで、どの資格を取得するにしても大切なのが「どんな学校で学ぶか」という点です。
資格そのものは全国どこで取得しても同じですが、学校ごとに カリキュラムの内容・国家試験合格率・就職実績・スポーツ業界とのつながり は大きく異なります。
例えば、柔道整復師や鍼灸師を養成する学校では、授業の比重が「医療寄り」か「スポーツ寄り」かで雰囲気が変わります。国家試験の合格率が高い学校はもちろん安心材料ですが、プロチームや地域クラブと提携して現場経験を積ませてくれる学校であれば、在学中からトレーナー活動の実践力を身につけられます。
また、学校を比較することで自分に合った学び方も見えてきます。授業時間や通学スタイル、学費の支払い方法など、ライフスタイルに合った学校を選ぶことが長く続けるコツです。
こちらのサイトでは、取得したい資格・学校の種類・通学時間帯(昼間部・夜間部)・エリア・都道府県などの細かい条件で、全国の専門学校・大学を調べて資料請求することができます!

まずはこのサイトで学校の強みや学費を比較してみましょう!
複数の学校の資料を見ることで、学校の強みや特徴も見えてきます。
他サイトでは、学校の掲載数が少なかったり、学費が分からないこともありますが…
この学校比較サイトなら
- 複数の学校を、一気に比較できる!
- 学校掲載数は、全国133校と圧倒的!
- 一番気になる学費も確認できる!
以下サイトからの資料請求で、大学・専門学校の学費が最大30万円引きとなります!
無料の資料請求をして、細かなカリキュラム内容やサポート体制を確認してみよう!