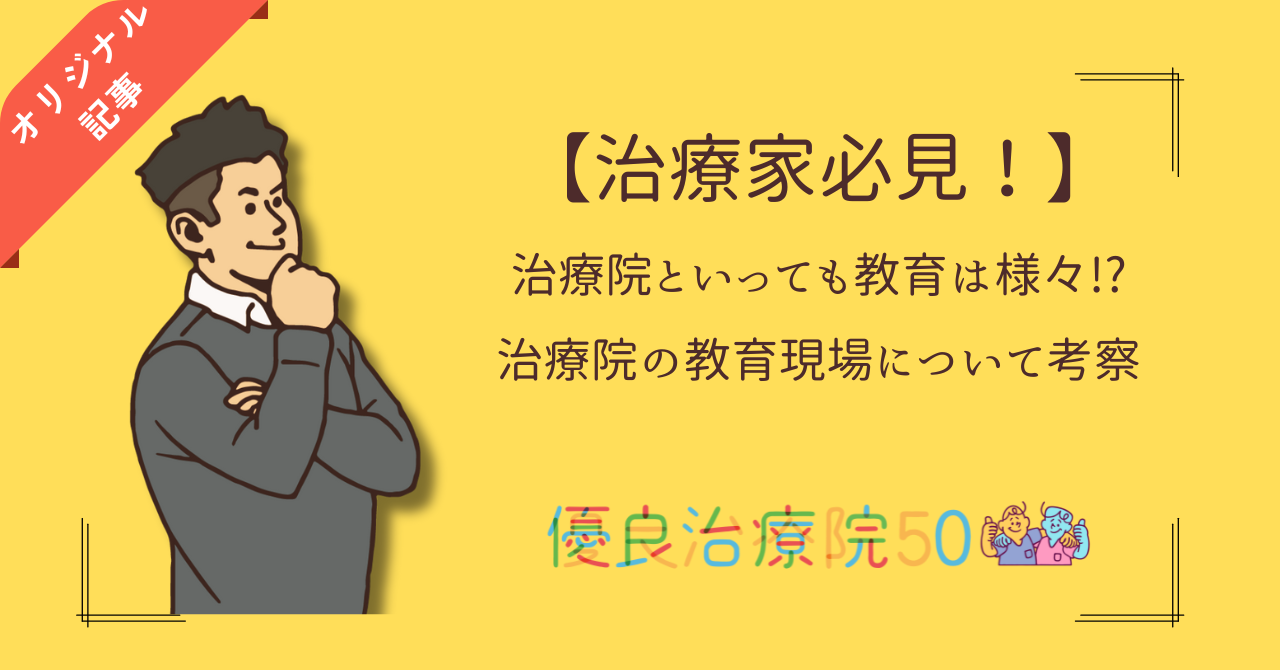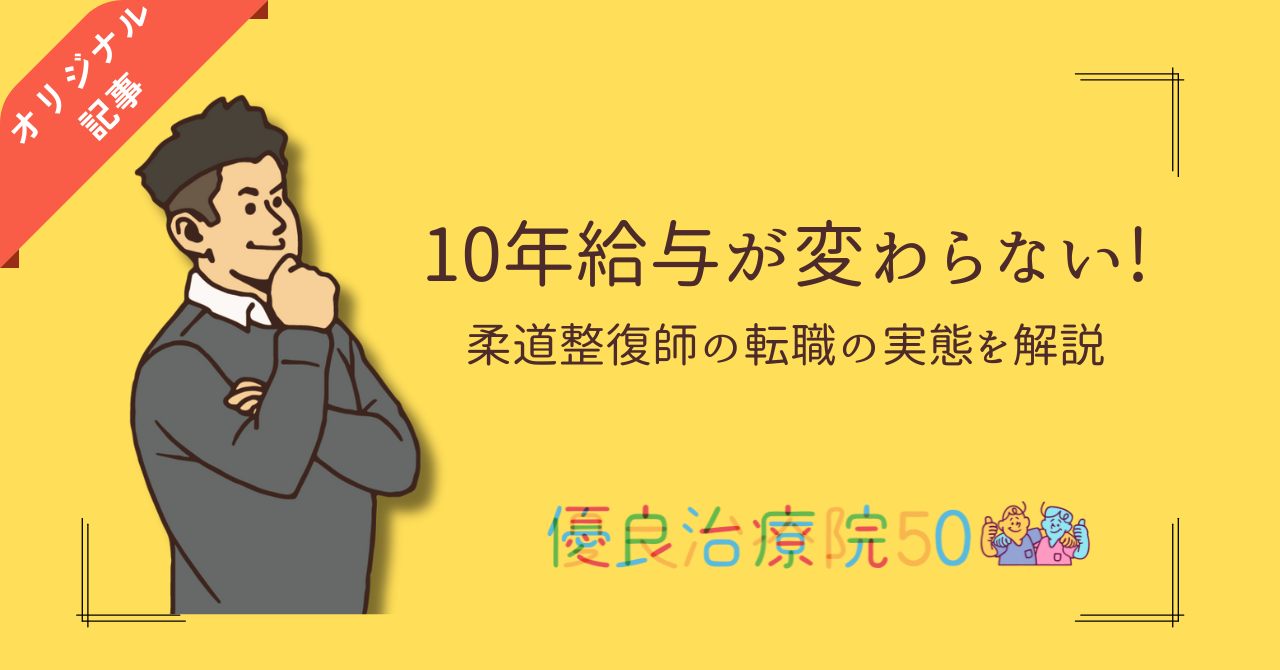柔整師が「理学療法士を取っておけば…」と後悔するポイントは?柔整師の強みを解説
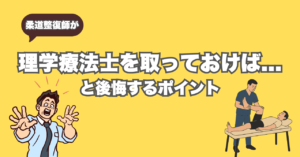
この記事の内容は、動画でも解説しています。
「やっぱり理学療法士を取っておけばよかったかも」
治療院業界で働き始めた柔整師から、そんな言葉を聞くことがあります。
人によって理由はさまざまですが、よくある理由は以下の通りです。
柔整師が理学療法士を取っておけば…と思う主な理由
- ・整形外科のPTと比べて、柔整師の給与が低い
- ・休日や勤務時間など、PTの方が働きやすそう
- ・職場によってはPTとの立場・関係に悩む
一方で、柔道整復師だからこそ得られるやりがいやキャリアもたくさんあります。
特に、施術の決定権や裁量、自費診療といった点では、柔道整復師ならではの強みを発揮できるケースも多くあります。
そこで本記事では、柔整師が「理学療法士になればよかった」と後悔するポイントを解説し、柔整師の強みの活かし方や働き方について解説していきます。
1986年生まれ。千葉市出身。3児の父。 2018年(株)じんじあいであ設立。 整骨院業界に採用という角度から貢献するため、教育・運営・店舗展開なども他面的にサポート。 人材供給だけでなくフォローアップ、院運営のコンサルティングも行う
なぜ「理学療法士になれば良かった」と思うのか?
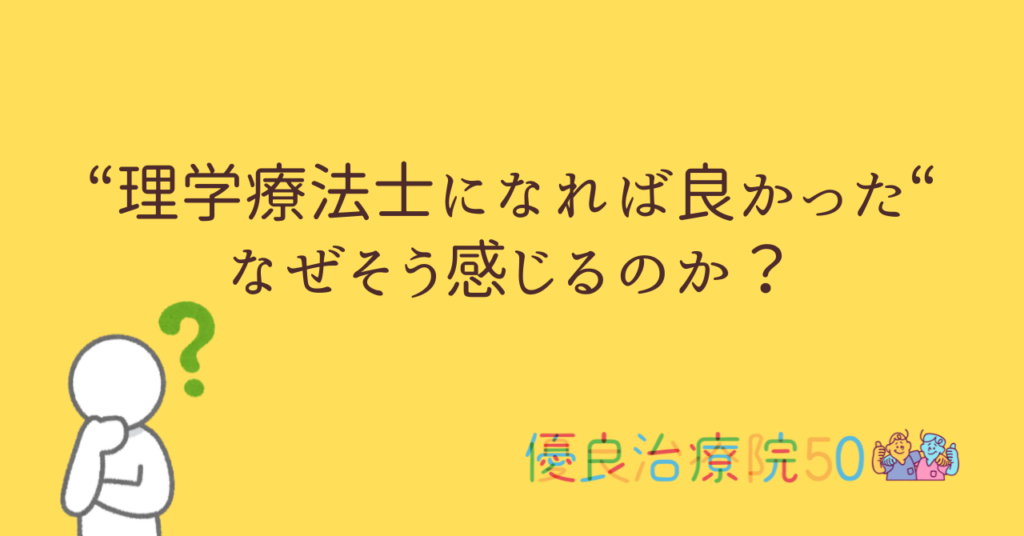
理学療法士と柔道整復師は、資格は違えど比較的近い領域で仕事をしています。
だからこそ、もし自分がPT(理学療法士)だったら給料がもっと高かったのでは?もっと自分の時間が取れたのでは?と感じてしまうかもしれません。
そこで、ここでは柔整師が「理学療法士になれば良かった」と感じるポイントをあげ、なぜそのような状況が起きるのか?という理由や背景を解説します。
給与・待遇面の差
最もわかりやすいのは給与です。
整形外科で働く場合、初任給の時点で理学療法士と柔道整復師の間に10万円近い差が出ることもあります。月に10万円の給与の差はとても大きく、年収では120万円ほど異なるケースもあるのです。
さらに整形外科では職場内の序列でも差を感じることがあります。「ドクター → 看護師 → 理学療法士 → 柔道整復師」となりがちで、立場や待遇に差を感じてしまう現実があります。
こうした給与面や序列を目の当たりにしたとき、多くの柔整師が「やっぱりPTの方が良かったかもしれない」と感じてしまうのです。
働き方の違い
次に大きな違いは働き方です。整骨院では営業時間に合わせて夜遅くまで施術が続くことも珍しくなく、終業が21時を過ぎるケースも多々あります。一方で、整形外科は病院であるため18時前後に終わるケースが多く勤務時間がとても安定しています。
働き始めてから「プライベートの時間を確保したい」「家族との時間を持ちたい」と考えると、この差はとても大きいはず。
知人や友人の働き方と比べたり、仕事とプライベートの優先順位が変化したりしたタイミングで、「PTの方が働きやすかったかも」と感じる人がいることも事実です。
キャリアの見え方の違い
将来のキャリア設計のしやすさも、理由のひとつです。
PTは病院勤務を起点に、訪問リハビリや介護施設、スポーツ現場など幅広いフィールドに進める道があります。資格として社会的に安定した立ち位置を持っているため、「将来どんな働き方をするか」の選択肢も幅広く、将来像を描きやすいのです。
一方で、柔道整復師は整骨院を中心としたキャリアになりやすく、環境によっては視野が狭くなってしまうかもしれません。そうした中で同世代のPTが活躍の幅を広げている姿を見ると、「あのときPTを目指していれば…」と考えてしまう人が出てくるのです。
このように、理学療法士は「給与・待遇」「働き方」「キャリア」の面が強いため、羨ましくなる気持ちもわかります。ただし、実は理学療法士にはない柔整師の強みもたくさんあります。
次の章では、理学療法士では出来ない、柔整師の資格を持つ人だから出来る業務ややりがいについてご紹介します。
柔道整復師ならではの強みとは?
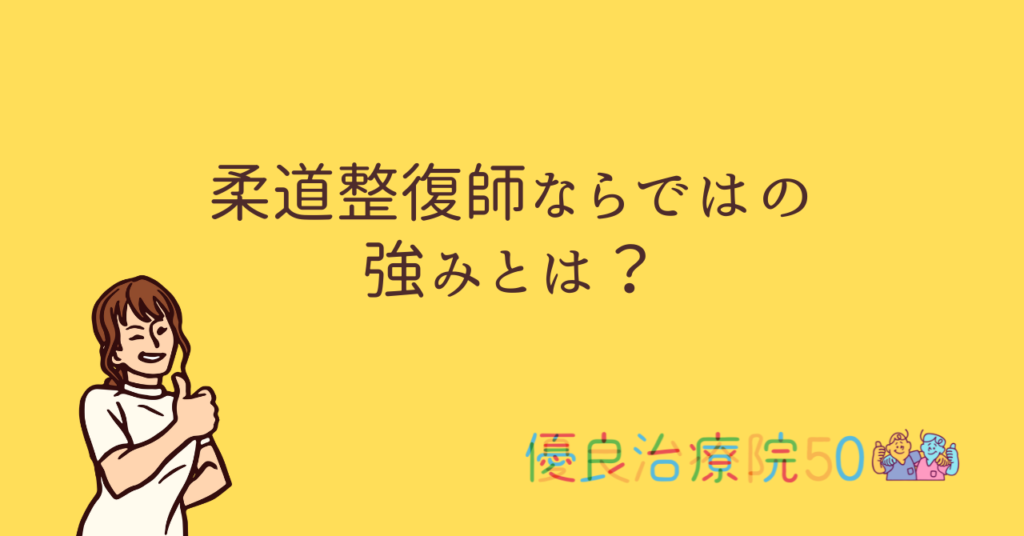
理学療法士と柔道整復師は「体のプロである」という共通点はあれど、資格が異なるため業務内容も異なります。
「理学療法士になれば良かった」という気持ちが少しでもある人は、それだけでなく、ぜひ「柔整師である自分が持っているもの」にも目を向けてみましょう。
柔整師は意思決定の自由度が高い!
整形外科で働く理学療法士は、ドクターの指示のもとでリハビリを進めるのが基本です。もちろん専門技術を発揮する場面はありますが、自分の判断で施術方針を決めることは難しく、「指示されたプログラムをこなす」という印象が強くなりがちです。
その点、柔道整復師は患者の状態をその場で見極めて、自分の意思で治療の方向性を決められます。状況に応じて「今日は肩の治療を優先しよう」「週1回の通院を隔週に変えて様子を見よう」といった臨機応変な判断を自分でできるのは大きな強みです。
患者から「あなたにお願いしたい」「あなたに診てもらいたくて通ってる」と言ってもらえる瞬間は、まさに柔道整復師ならではのやりがいです。
患者と直接向き合って自分なりに施術ができる点は、理学療法士にはない大きな魅力だと言えるでしょう。
柔整師なら自費診療ができる!
自費診療は、整骨院で働く柔道整復師が得意なフィールドです。
さまざまな制限がある保険診療ではなく自費診療に取り組むことで、1人の患者にしっかり時間をかけて施術できます。またその施術内容も自由度が高いため、自分が習得した技術を惜しみなく発揮でき、大きなやりがいを感じるでしょう。
こうした高い技術力を持ち合わせている柔整師は、経済的な安定・時間の自由・やりがいが揃い、「柔道整復師になってよかった」と実感する人も多くいます。
独立開業の道もある柔整師は、取り組み次第で技術も収入も伸ばせる資格なのです。
理学療法士から見ても、柔整師は魅力的
柔整師であるあなたが「理学療法士はいいな」と思うように、理学療法士から見て「柔整師はいいな」と思う点もたくさんあることが分かったと思います。
特に、ドクターの指示を待つ理学療法士の立場から見ると「自ら患者を診て治療の方針を決めることができる」という意思決定力は大きな魅力なのです。
柔整師だからこそ治療技術を磨け
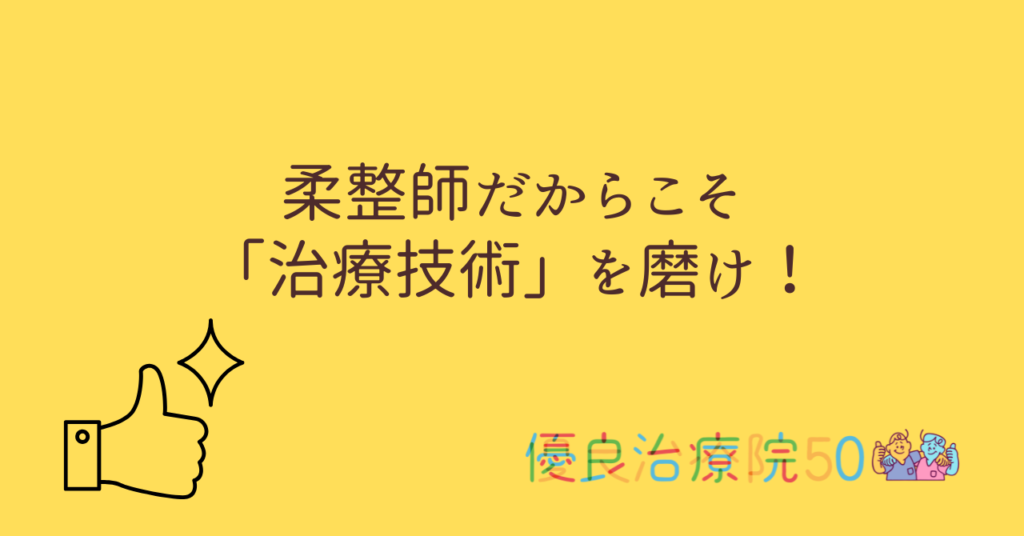
「理学療法士にすればよかった」と後悔する人の多くは、待遇や働き方の差に着目しています。
でも、思い出してください。なぜあなたは柔道整復師の道を目指し、国家資格に向けて頑張って勉強したのでしょうか?
努力して獲得した柔道整復師の資格をしっかりと自分の強みとして発揮するためには、マニュアル通りに施術するのではなく、自分で考えて治療を組み立てる力が欠かせません。
もちろんマニュアルがすべて悪いわけではありません。治療の基礎を学ぶ上では大切な手がかりになります。ただし、そこに頼りきりになってしまうと自分の頭で考えた治療ができなくなり、どの患者さんにも同じ説明・同じ施術になってしまいます。
そうなると、柔道整復師の「施術の自由度がある」「意思決定ができる」という強みを活かせません。
「骨盤が歪んでいます」「この3パターンで施術します」といった固定した対応ではなく、患者一人ひとりの症状をしっかり評価し、最適な施術を選べることが柔整師の強みだからです。
柔整師は患者さんから“選ばれる”立場だからこそ、若いうちから技術を磨いておくことが重要です。自分で培った技術を使い、自分の手で治せる患者さんが増えるほど、施術の幅も広がり、やりがいも大きくなっていきます。
柔整師は職場選びが超重要
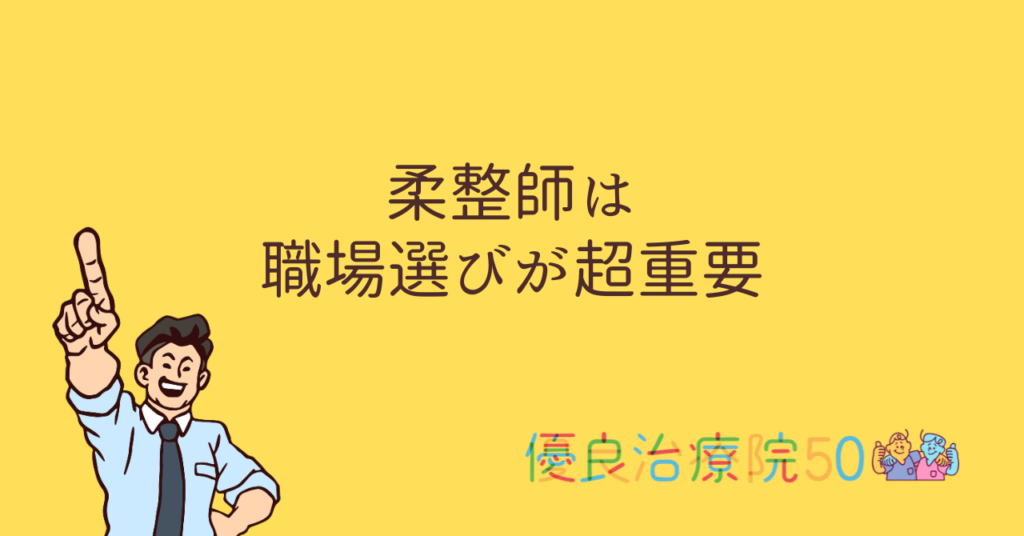
柔整師において職場選びはとても重要です。
実際に「給与」や「休みの多さ」などの条件だけで決めてしまい、後になって「思っていた環境と違った」と後悔する若手治療家をたくさん見てきました。
もちろん生活のために待遇は大切ですが、それ以上に重要なのはその環境で治療家として成長できるかという視点です。
具体的には、以下のようなポイントをチェックしておきましょう。
- 勉強会や研修の充実度
技術向上に本気で取り組んでいる院は、時には院を休みにしてでも全員で勉強会を行います。トーク練習や営業研修ではなく、技術研修の機会が多いかどうかは、治療家として成長できる職場かどうかを見極める大切な判断ポイントです。 - 質問できる雰囲気があるか
中には勉強会や研修の場を設けていない院もあり、特に個人院の場合は現場に立って臨床を積みながら技術を学ぶケースもあります。このような院では、疑問が出たときに気軽に先輩や院長に相談できる風通しの良さが重要です。 - 自分の理想の治療家像に近づけるか
「患者さんから感謝される治療家になりたい」「スポーツ選手を支えたい」など、自分の理想に近づける職場かどうかも大切です。院の理念や取り組み、そこで働く先輩の姿が、自分の描く治療家像と重なっているかを意識しましょう。
治療院とひとことで言っても、院によって大切にしているものは異なります。
技術を大切にしている院もあれば、効率や売上を過剰に求める院もあり、院の規模も個人院から大手グループ院までさまざまです。
柔整師としての強みを活かすためにも、職場選びはとても重要であることを覚えておいてください。
自分はどんなタイプの整骨院が合うのか分からない…という方は、ぜひ治療家専用の職場適性検査を受けてみてください!質問に答えるだけで自分の考えや理想に合った治療院タイプが分かります。

まとめ
理学療法士と柔道整復師の間には、給与や待遇、働き方に違いがあります。
「PTを取ればよかった」と感じる瞬間もあるかもしれませんが、柔道整復師だからこそ発揮できる強みも確かに存在します。
大切なのは自分は何を大事にしたいのかを整理し、その価値観に合う職場を選ぶこと。
まずは柔整師としての強みを意識して、その強みを伸ばせる職場や環境を探してみましょう。
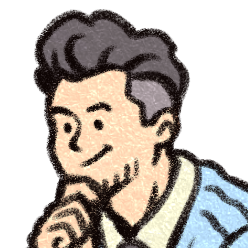

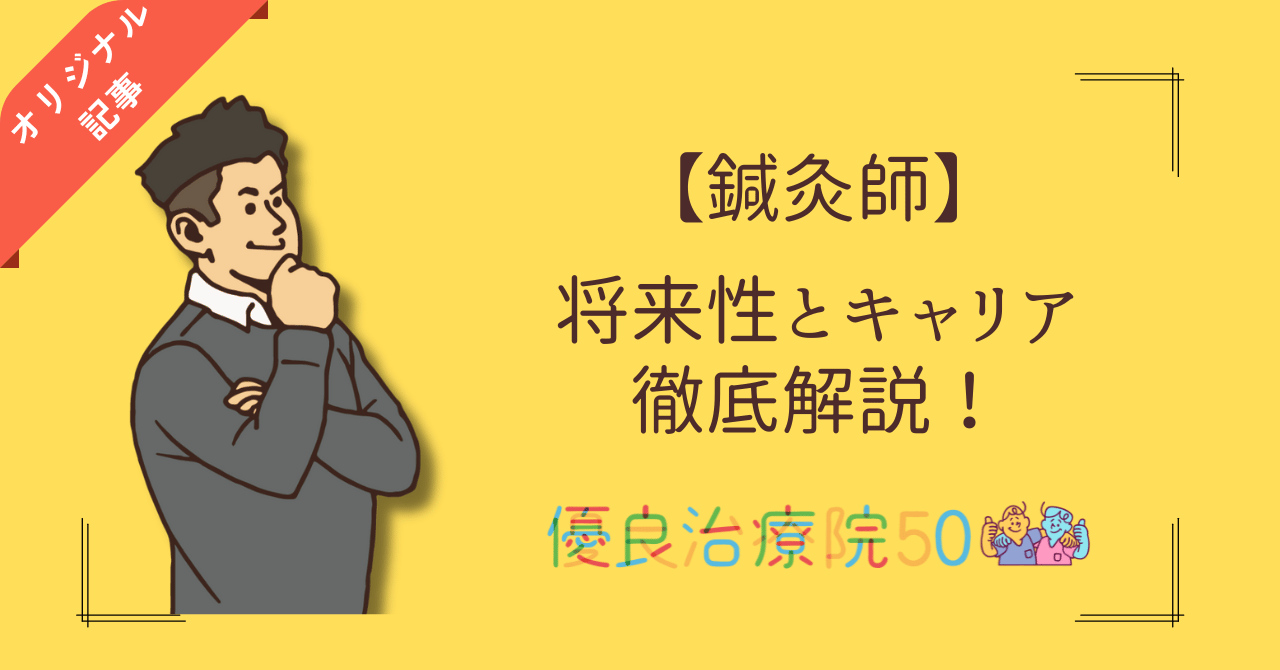
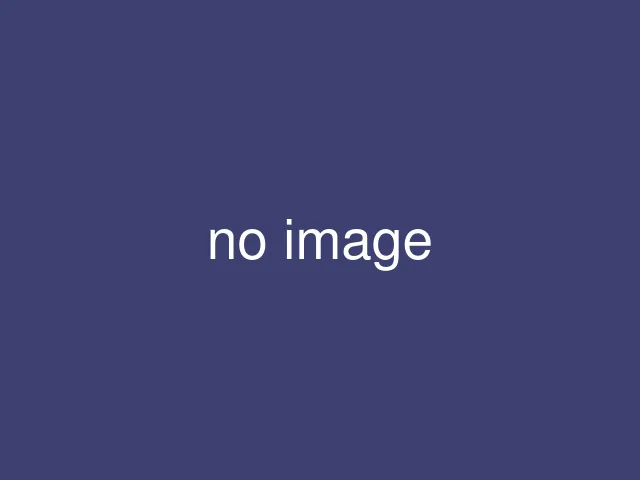
.png)